Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2022年 松本先生コラム第2回
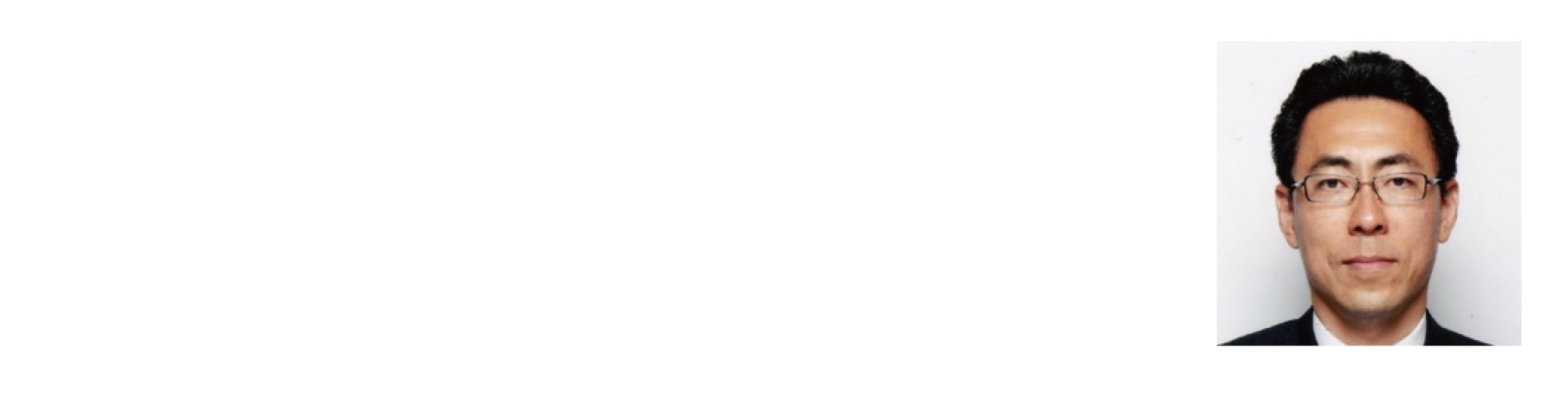
2018年6月に食品衛生法の改正によってHACCPが制度化され、原則として食品事業者はHACCPに基づいた衛生管理が求められることになりました。猶予期間を終えて、2021年6月からHACCPの制度化が施行になり、食品事業者においてHACCPは運用の段階に入っていると思われます。そこで第2回では、HACCPやそれを含むFSMS(Food Safety Management System:食品安全マネジメントシステム)を現場で効果的に運用するための実践のポイントをお伝えします。
筆者が初めて本格的にHACCP に関わったのは1990 年代の終わりです。当時、食品企業で海外事業の技術担当者として、アメリカ 法人の工場を生産と品質保証面でサポートする役割を担っていました。ある時、担当の工場がウォルマート社から取引を継続する 条件として、AIB*1 の監査で875 点以上(1,000 点満点)の取得を課せられたため、アメリカに2 カ月間滞在して現地のQA マネー ジャーをサポートすることになりました。AIB の要求事項にHACCP の要素が含まれ、その土台となるGMP の課題や問題を改善し、 製造工程のハザード分析を見直すところから着手しました。QA マネージャーは着任して間もない状況でしたが、製造現場をよく 理解しており、包装工程とペストコントロールに問題があることを認識し、これを機に問題を解決しようと考えていました。結果、 監査で875 点をクリアすることができ、製造現場の理解と目的意識の重要性を学びました。その後、国内食品工場の品質保証の 責任者として、GFSI 承認認証規格*2 であるFSSC 22000 を導入し、また海外法人で複数の工場を統括する品質保証の責任者として HACCP を利用して品質トラブルを削減する機会があり、かつての学びが大いに役立ちました。このような経験から得たことを次に まとめました。
*1:AIBはAmerican Institute of Bakingの略で、1919年から活動を開始したアメリカ国内の製パンや製粉メーカーの技術者育成機関です。日本国内では2001年から一般社団法人日本パン技術研究所によって監査が実施されています。
*2:GFSIはGlobal Food Safety Initiativeの略で、GFSIで定められたベンチマーク要求事項に整合すると承認を受けた規格をGFSI承認認証規格と言います。FSSC 22000やJFS-Cがあります。

関係部署から実務に精通した人が集まってHACCP チーム(FSMS の場合、食品安全チーム)が編成され、協力 してシステムを導入する、というのが理想です。しかし実際は、品質保証や品質管理等の一部の人が導入を進めて、 チームとして機能しない、ということはありませんか。HACCP の7 原則12 手順の手順1 の前に、システムを 導入する工場、或いは組織内で考え方の合意をして参加する部門のメンバーにコミットさせることが有効なシス テムを構築するために非常に重要です。そのために、品質トラブルを削減するというような組織としての目的 意識が有効であると思います。
導入したけれども、クレームやトラブルが減らないから意味がなかった、とHACCP を否定する取引先がありま した。その取引先ではハザード分析をしているのに同様のトラブルの発生が収まらない状況でしたが、HACCPと 品質トラブルの是正が結び付いておらず、運用の仕方に原因があるとわかりました。例えば、異物クレームが 発生したら、製造工程でのハザード分析を見直し、見落としがあったら管理を強化する、という繰り返しによって システムの有効性が上がります。また、すぐに結果がでるものではなく、ある程度時間がかかることも認識する 必要があります。筆者の国内工場や海外での経験では、目に見える成果が出るまで2 年から3 年かかりました。
製造工程や製造する製品、使用する原材料等、システムの対象は変化します。食品安全に関わる変更が生じた 場合は、ハザード分析を見直し、新たなHACCP プランを作成するなど、変更に対応しなくては効果のある システムは維持できません。製品の改廃が頻繁に行われる製造工程では労力がかかりますが、有効なシステムを 維持するためには、変更の都度、対応する必要があります。
システムが導入されたらCCP は重点的に管理されます。筆者が品質保証の責任者を務めていた6 年間で、国内 工場と海外法人の工場で発生した重大な品質トラブルはCCP の管理の不備ではなく、一般的衛生管理の不備で 発生しました。誰もがCCP の管理が重要であることは認識しています。しかし忘れてはいけないのは、CCP の 設定は一般的衛生管理が適切に行われていることを前提にして行われているということです。
建屋や施設等でHACCP 対応と謳われているのを見かける場合がありますが、本来 HACCP システムはソフト (手法) なので、建屋や施設等を新築・改築時にシステム導入する場合を除いてハードへの投資が先行することは なく、投資ありきではありません。しかし、ハザード分析の結果、食品の安全性を確保するために投資をしなくては いけない場合があります。従って、HACCP システムの導入において、必要な投資を効果的にすることができると 言えます。先に紹介したアメリカでのHACCP の取組では、食品安全が懸念された包装工程において、充填機を 囲うという必要最小限の投資で改善しました。
GFSI 承認認証規格の中に食品防御に関する要求事項があります。筆者は前職で食品防御に関する社内ルールの 作成から関わり、国内の食品工場、次いで海外の工場で対応を進めるという役割を担いました。カメラの設置、 製造エリアにおける出入口管理(備品等の持ち込みの管理)、指紋認証、施錠等の様々な対応方法があります。 現場の担当と製造現場で対応が必要な箇所を回り、一カ所ずつ最適な方法を取りました。
意味が分からない文書や記録、審査のための準備等、システムには良い印象を受けないこともあると思います。それだけに筆者は 国内の食品工場や海外法人の品質保証の責任者の時に、意味のあるシステムにしようと試行錯誤しました。今回はその時に考えた 概要をHACCP とFSMS の実践のポイントとしてお伝えしました。ご参考になれば幸いです。
出典
1)松本隆志(共著)『, 実践 微生物制御による食品衛生管理』「第3 編HACCPと現場対応 第2 章食品製造工場へのHACCP導入と運用の実際 p.153-169」, 出版:株式会社エヌ・ティ・エス, 2020年12 月。
2) 松本隆志(共著)『, 国内外における食品衛生の関連法規と実務対応に向けた基礎知識「』第2章HACCP義務化に伴う影響と関連制度概要 P.27-53「」第5章食品リコール情報の報告制度の創設 p.90-96」, 出版:株式会社情報機構, 2020 年12 月。
食品事業者における品質保証業務
知りたいけど、誰も教えてくれなかった品質保証業務の全体像について
食品事業者に役立つ品質保証・品質管理 品質保証体制の構築
―HACCP 導入後の品質保証関連の取り組みについての提案―
食品事業者に役立つ品質保証・品質管理
フードサプライチェーンの品質保証 ―原材料管理―