Home » 学術・技術情報 » 松本先生コラム トップページ » 2023年 松本先生コラム第6回
東京海洋大学 学術研究院
食品生産学科部門教授
2023年度のテーマに人材育成、品質保証体制、サプライチェーンにおける品質保証、リスクマネジメントを取り上げました。品質保証や品質管理に関わる方はそれらの重要な業務を別々に行っているのではなく、関連付けているものと思います。第6回は、2023年度のテーマを関連付けて、「トラブル防止」について筆者が学んだことをお伝えします。
筆者は食品企業において品質保証の業務の一環として、品質監査を担当し、監査を実施するだけではなく、監査員の要件を決めて人材育成を行いました。逆に、工場の品質保証の責任者の立場で監査を受ける経験もしました。品質監査は、原料の調達先や製造委託先を選定し、取引開始後は安定した品質の原料や製品を提供してもらうために継続的に実施するものです。一方で、品質監査ほど、品質保証や品質管理の人材育成に役立つものはないと思いました。監査では、要求事項に基づくチェックリストや製造現場の視察によって相手先を評価する他に、品質保証に関する取り組みやリスクマネジメント、人材育成に関する情報交換や議論を行っていたからです。
コロナ禍でオンラインによる監査が行われるようになったと思いますが、現地に行くことによりわかることがありますので、今後も実地の監査は続くのではないでしょうか。
監査では全ての要求事項について時間をかけて満遍なく確認することは難しいです。限られた時間の中で、相手先との取引の開始や継続の是非を判断し、是とした場合でもリスクがあれば、トラブルを防止する必要があります。次に、筆者がかつて監査員教育の際に監査のポイントとして挙げていたことを、事例を交えてご紹介します。

HACCPの7原則12手順の手順5は「フローダイアグラムの現場での確認」です。現場確認が重要であるのはこれに限ったことではありません。決めたルールが製造現場で変わっていたり、守られていなかったりすることがあると思います。
ある海外のサプライヤーでは、工程管理のために膨大な記録をしていました。30分かかる原料の混合工程で1分おきに混合の様子を記録することになっていましたが、1分おきに記録すべき理由はありませんでした。一方で、トラブルに関わる記録が不十分で原因究明に至らないという、ちぐはぐさがありました。管理職が現場を理解せずにルールを考えて導入していたためです。
また他のサプライヤーでは、製造現場では、作業員が作業をしやすいように、検査機の設定を変更して異常を検出しても機械が止まらず、不具合品が流れてしまうことがありました。 システムやルールが形骸化していないことを確かめるために、製造工程のルール、特にリスクがありそうな工程を対象に、その内容が妥当であり、製造現場で守られていることを確認していました。
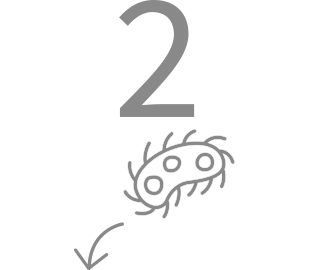
・HACCPシステムをこれから導入しようという事業者から、何から手を付けるべきかというアドバイスを求められたら、まず2S(整理整頓)から始めるように伝えます。過去の事例として、原料に異物混入の問題が発生し、サプライヤーを訪問した際、製造現場に不要物が多く(整理ができていない状態)、備品や工具などを保管する場所はありましたが、動線が悪いために、至る所に備品などが置かれていました(整頓ができていない状態)。2Sに加え、製造現場の出入口管理(私物の持ち込み禁止など)ができていれば、食品防御(フードディフェンス)にも配慮されていると思います。
・野菜に付着した異物や虫を取り除くのは非常に難しいことです。ある海外のサプライヤーで、野菜の表面を水で洗い、目視で異物を取り除く工程がありました。その原料で虫が発生したトラブルがあり、原因を調査したところ、教育不十分な作業者が従事していたということもありましたが、それよりも冬場で水が冷たく、野菜を十分に洗えていなかったことが主の原因であることがわかりました。対策の一つは冬場にお湯を使うということになりましたが、監査での現場確認の前に、本来はサプライヤーの管理者に把握しておくべきことでした。

筆者が工場で品質保証の責任者の立場であった時、異物混入防止と並んで、最も注意を払っていたことです。加工度の低い原料や単一の原料を製造するような場合を除いて、原料の保管から充填工程まで、クロスコンタミネーションの可能性、製品(原料)の製造順番、製品の切替、洗浄方法を念入りに確認しました。製造品目が多い場合は、変更管理のルールがあって、適切に行われていることも重要なポイントです。

・原料でトラブルが発生した際に、最も困るのは範囲が特定できないことです。そのため必ず工程管理の記録と製造現場でトレーサビリティを確認しました。ある国内のサプライヤーでは、発酵工程を含むバッチ式の工程で製造されていました。ある工程では前後のロットと一緒になり、その次の工程ではわかれるといった工程であり、監査の時にトレースができないという状況でしたが、その原料が製品の製造に欠かせず、取引をする必要があったため、サプライヤーと協力してトレースできるようにロット管理を見直しました。
・原料が一次産品の場合、農薬や動物用医薬品が適切に使用されていることを受入検査だけで確認することはできないので、監査により現地で使用状況や記録を確認し、サプライヤーに保証してもらいました。中にはトレーサビリティが難しいものがあり、検査で確認する場合もありました。
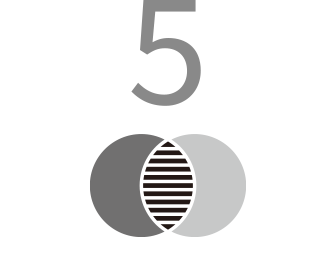
ヒトの動線が汚染作業区から清潔作業区に向かうのが良くないことはわかりますが、古い工場・建屋の場合、物理的に動線を変えるのは難しく、ゾーニングはそのままで対策をしない場合、異物混入や微生物汚染の原因になる可能性があります。投資をすれば解決するでしょうが、それは最後の手段であり、如何に異物混入や微生物汚染のリスクを捉えて対処しているか、について確認しました。例えば、作業区を移動する場合に、靴を履き替える、作業着を替える、手洗いをするなど、トラブルが発生しないようにリスクを低減するということです。

自社で製造する場合は、常在菌に配慮して加熱殺菌条件を設定すると思いますが、原料由来と製造委託先の微生物は監査ではわかりませんので、検査で確認する他はありません。原料由来で想定以上の耐熱性菌が検出されたことがあり、従来よりも厳しい加熱殺菌条件を設定したことがありました。
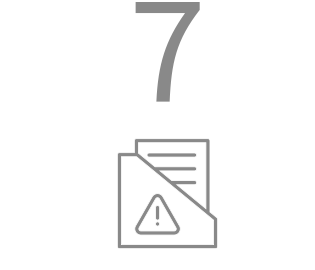
監査の際に、工程管理と品質管理の記録を工程に沿って確認しましたが、かなりの割合で、記録漏れ・間違いが見つかりました。トラブルによって記録する項目を増やすことはあっても減らすことは難しいと思いますが、中には項目が多く、重要な記録が目立たないためか、不備の場合がありました。記録によってトレースができ、かつHACCPのCCPに関わるものは確実に記録してほしいものです。
20年以上前に品質監査に関わるようになった時に上司からアドバイスをもらいました。「原料サプライヤーはその原料に関するプロであり、また製造委託先は自社で作れないものを作ってもらうプロだから、訪問する前に、その原料・製品や会社のことをしっかり勉強して臨むように。自社のこと(システムやルールなど)を説明して議論する機会があるから、当然自社のことも理解していないと話にならない。」 取引先を尊重し、協力して良い製品を作る、ということを教えられました。
このアドバイスによって後の筆者の品質監査は大きく影響を受けました。筆者が監査を受けた時は、一方的に指摘されることが多かったのですが、監査をする側の場合は、問題があれば協力して解決するようにしていました。原料サプライヤーや製造委託先はフードサプライチェーンを構成する仲間なので、考え方や取り組み姿勢で品質監査は有効で有益なものになると思います。
近年、GFSI承認認証規格では食品偽装防止や食品安全文化の醸成に関する要求事項が加わっています。要求事項は増える一方で、監査をする側もされる側も負担が大きくなっていると思います。もし、今筆者が監査をする場合、どちらの事項も取引先として信頼できるかどうかをポイントとするでしょうか。現在、調査研究をしていますので、何かの機会にご紹介したいと思います。
2023年度の最後のコラムは、まとめの意味もあり、「トラブル防止」をテーマにして、かつて筆者が品質監査において確認していたポイントを挙げました。その他に、悪い事例がなくて挙げませんでしたが、品質管理でしょうか。様々な食品企業と関わる中で、これらのポイントは今でも変わっていないと考えます。品質保証・品質管理の強化に少しでもお役に立てましたら幸いです。